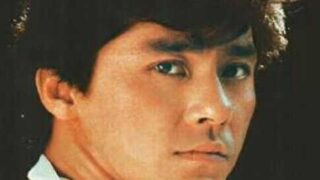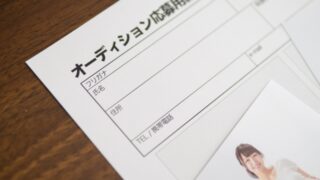幻の深海魚といわれるリュウグウノツカイが今月11月11日朝富山湾で水揚げされ、生きて泳ぐ貴重な姿をカメラがとらえました。
幻想的な名前にふさわしい、銀色の体と赤色のひれの持ち主であるリュウグウノツカイ。
数ある深海魚のなかでも高い知名度を誇っていますが、その生態についてはあまりよく知られていません。
そこで今回は、謎多きリュウグウノツカイについて調べたことを、詳しくご紹介していきます。
4m級リュウグウノツカイ2日連続で水揚げされる
高知県室戸市で幻の深海魚と言われるリュウグウノツカイが定置網にかかりました。大きさは4m級。しかも、2日連続です。
13日、高知県室戸市にある「むろと廃校水族館」のTwitterアカウントに投稿されました。
幻の深海魚 リュウグウノツカイです。
小学校の旧校舎を改修した「むろと廃校水族館」には、日ごろから、漁の網にかかった生き物が持ち込まれ、展示されています。
そうした魚たちは転入生と呼ばれていて、最初の連絡は、12日でした。
● むろと廃校水族館 空田知久 学芸員
「定置網にリュウグウノツカイがかかっている」と電話をいただいて、サイズがどれくらいだろうと思って漁港に行ってみてみると、船の横幅を占めるくらいの大きさで、漁師さんに手伝ってもらいながら水族館に搬入した。
大きさは3.7m。学芸員の空田さん(身長165cm)と並ぶとその大きさがよくわかります。ただ、これだけでは終わりませんでした。
● むろと廃校水族館 空田知久 学芸員
13日も、「またリュウグウノツカイがかかったぞ」と漁師さんから電話をいただいて、きょうもまた漁港に行くと、きのうよりさらに大きい4mを超えるリュウグウノツカイが船にいて… なんと2日連続でリュウグウノツカイが網にかかかったのです。
大きさは12日を上回る4m5cm! 空田さんと女性スタッフが並んで寝てみても、敵わない大きさです。(空田さん:165cm 女性スタッフ:154cm)
2日連続でやってきた珍しい「転入生」で水族館は大騒ぎだといいます。
●むろと廃校水族館 空田知久 学芸員
1匹目の時点でだいぶ驚いたが、2日連続ということで標本にしようか、どういう対応しようか水族館でもいま大騒ぎしている。リュウグウノツカイが高知の室戸で2日獲れるというのは本当に珍しいので、エサがあったのか、好漁場だったのか、海水温の変化なのか、なかなか興味深い話です。
2匹とも、港に着いた時点ではすでに死んでしまっていたため、むろと廃校水族館では今後、胃の中身や寄生虫などの調査を行い、標本にするか、冷凍保存してイベントなどで展示するか、検討していきたいとしています。

テレビ高知提供
竜宮城からの使者リュウグウノツカイってどんな生きもの
リュウグウノツカイは、アカマンボウ目リュウグウノツカイ科に属する深海魚です。
細長い銀色の体は平均3~5m、中には10mを超える個体もあり、硬骨魚類のなかでは世界最長とされています。
体重も30~50kg程度ありますが、海流に乗ってゆらゆらと立ち泳ぎする姿は非常に優雅です。
また、見た目の美しさにも定評があり、薄い青色の線が並んだ銀色の体に、鮮やかな赤色の背びれがたなびくさまは、とても神秘的です。
腹びれの先端がボートに使うオールのような形をしていることから、「Oarfish」という英名がつけられています。
日本では幻想的な姿がおとぎ話に出てくる竜宮城をイメージさせることから、「竜宮の使い(リュウグウノツカイ)」という和名で呼ばれています。
ただ、和名の由来を示す文献が見つかっていないため、誰が・どんな思いで名付けたのかは明らかになっていません。
生息場所は幅広く、世界中の海域において水深200~1,000mあたりに分布しており、日本では北海道~九州の太平洋側と、日本海側、沖縄本島近辺などに生息しています。
体のサイズに見合わないプランクトンやオキアミなどの小さな生物を主食としていますが、それでも寿命は20年に及ぶともいわれています。
縦に平べったいリュウグウノツカイで、特に目立つのは鶏のトサカのような頭部に近い背びれ。最初の数本から十本が特に長いのです。
ひれは柔らかく、背びれは毛のように背部から最後部まで続いています。
胸びれも優雅なループタイのように長いです。なんと歯もウロコもウキブクロもなく、かなり変わった魚といえるでしょう
リュウグウノツカイはお腹が減ると自分の尾っぽの一部を切って体力温存
リュウグウノツカイが生息している深海は生きものが少ないため、いつでもエサにありつけるわけではありません。
何日もエサを捕食できず、極度の飢餓状態に陥ったリュウグウノツカイは、なんと自分で自分の尾部の一部を切り落としてしまいます。
長い体をコンパクトにまとめることでエネルギーを温存し、生き延びるための手段であると考えられています。
体を切ったら、かえって弱ってしまうのでは?と思うところですが、リュウグウノツカイは生きていくために必要な臓器が体の中央より前に集中しているので、尾部の一部を切っても生きるのに問題はないのだそうです。
ちなみに、ほかの魚に襲われたときや、漁の網にかかりそうになったときも、尾部の一部を切って逃げてしまうことがあります。
トカゲのしっぽ切りに似ていますが、しばらくするとしっぽが再生するトカゲとは異なり、リュウグウノツカイは一度尾部の一部を切ると二度と生えてくることはないと言われています。
実際、これまで目撃されてきたリュウグウノツカイのなかには、尾部の一部が切られていた個体も多く見られたそうです。
生きたままのリュウグウノツカイに見られるのは難しい!
リュウグウノツカイをテレビなどで見ることはあっても、水族館などで生きた状態で目にする機会はほとんどありません。
水深200~1,000mの深海で暮らすリュウグウノツカイを生きたまま捕獲するのは難しいうえ、そもそも大きいので不自由なく遊泳させてあげられる水槽を持っている園館も少ないことや、水槽で深海の状況を再現するのは困難であることから、現時点でリュウグウノツカイを飼育するのは非常に難しいとされています。
ただ、2019年2月に、沖縄美ら島財団総合研究センターが世界で初めてリュウグウノツカイの人工授精と人工孵化に成功し、大きな話題を集めました。
残念ながら、約20匹の稚魚はわずか数日で全滅してしまいましたが、今回の研究をもとに詳しい生態が解明されれば、近い将来、生きたリュウグウノツカイを水族館で見ることができる日がくるかもしれません。
リュウグウノツカイには古くから多くの謎と伝説があった
リュウグウノツカイは、神秘的な見た目と、めったに遭遇できない珍しい存在であることから、さまざまな伝説と関わりがあります。
ここでご紹介するのはあくまでも「伝説」であり、科学的な根拠や証拠となる文献が存在しているわけではありませんので、おもしろ話のひとつとしてお楽しみください。
リュウグウノツカイが海面付近に現れると災害が起きる
リュウグウノツカイは通常、水深200~1,000mに生息しているため、海面付近で目撃されたり、捕獲されたりするのは非常に稀なケースです。
そのせいか、リュウグウノツカイが海面付近に現れるのは災害が起こる前触れとされており、日本では忌み嫌われることも少なくありませんでした。
今のところリュウグウノツカイと災害の関わりは解明されていませんが、東日本大震災が起こる1~2ヵ月前や、2018年に発生した大阪北部の地震の前日にリュウグウノツカイが目撃されていることから、災害と関連づけて考える人も多いようです。
リュウグウノツカイを食べると不老不死になる
日本には、古来より人魚の肉を食し、不老不死になった女僧「八百比丘尼(やおびくに)」の言い伝えが残されています。
比丘尼が食した人魚の正体については諸説ありますが、鎌倉時代に編まれた世俗説話集「古今著聞集」にて、「人魚なのかもしれない」と描かれた大魚の特徴がリュウグウノツカイと似ていることから、人魚=リュウグウノツカイとする説もあるようです。
ちなみに漁網にかかり、リュウグウノツカイを食べた人の話では、水分が多く薄味のため、味はイマイチだということです。
リュウグウノツカイが網にかかると豊漁になる
災害の前触れとされるリュウグウノツカイですが、その一方で、網に掛かると豊漁の兆しと喜ぶ人もいます。
普段は深海にいるリュウグウノツカイが海面近くまで浮上するのは、エサとなる魚がたくさんいるからというのが主な理由のようです。
実際、ノルウェーなどでは、ニシンが大量に釣れるときにリュウグウノツカイが目撃されることがあるため、「King of Herrings(ニシンの王)」という異名が付けられています。
国や地域によって吉兆にされたり、凶兆にされたりする不可思議さも、リュウグウノツカイの神秘性を高める要因になっているのかもしれません。